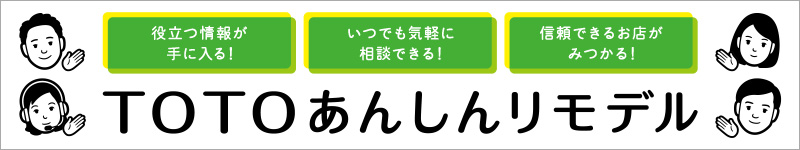社長ブログ
第一種換気と第三種換気の違い|子どものアレルギーに強い24時間換気の選び方

小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、室内の空気の質やアレルギー対策について特に心配されることが多いでしょう。
建物の高気密化が進んだ現代の住まいでは、24時間稼働する換気システムが、健康的な空気環境を維持するための要となります。
この記事では、換気計画の中でも特に普及している第一種換気と第三種換気の仕組みや、アレルギーの原因となる物質を効果的に取り除くための選び方、
そして失敗しないための実務的な計画の立て方について、住宅アドバイザーの視点から詳しく解説します。
🏠 暮らしが良くなる理由:換気計画がもたらす「安心」な空気環境
室内に「入れない」換気システムの考え方
アレルギー対策の基本は、外気の汚染物質を極力室内に入れないことです。
換気システムの中には、給気(外気を取り込む側)に高性能なフィルターを設置できるタイプがあります。
このフィルターの性能によって、花粉や細かなPM2.5の粒子をシャットアウトし、きれいな空気だけを室内に取り込むことが可能になります。
また、機械で強制的に給気と排気を行う第一種換気システムの中には、室内の気圧をわずかに高く保つ「正圧」の状態を作り出すものがあります。
正圧にすることで、窓や扉の隙間からフィルターを通らない汚れた空気が侵入するのを防ぐ効果が期待できます。
お子様がアレルギー体質である場合は、給気フィルターの性能と、気圧制御の仕組みを重視することが大切でしょう。
24時間換気で実現する「住まいの深呼吸」と快適な睡眠
建築基準法に基づき、すべての新築住宅には24時間換気システムの設置が義務付けられています。
これは、室内の二酸化炭素濃度や生活臭、水蒸気、そして建材から発生する微量の化学物質を常に排出し、新鮮な空気を取り込むためです。
就寝中も換気が続くことで、家族が眠っている間に呼吸によって上昇する二酸化炭素濃度を適度に抑え、質の高い睡眠環境を維持できます。
朝起きたときに空気がこもっていると感じたり、頭痛がしたりする状態は、換気が不足しているサインかもしれません。
24時間稼働を前提とした計画で、家全体が常に新鮮な空気に入れ替わる状態を確保しましょう。
要点:換気計画は、高性能フィルターや正圧制御によりアレルギー原因物質の侵入を防ぎ、24時間稼働で快適な睡眠と健康的な室内空気質を維持します。
🛠️ 設計・計画の考え方:第一種・第三種換気システムの選び方

換気システムには、大きく分けて三つの方式がありますが、住宅で主に用いられるのは「第一種換気」と「第三種換気」の二つです。
それぞれの仕組みと特徴を理解し、ご自身のライフスタイルや重視する性能に合わせて選択することが重要です。
第一種・第三種換気の「方式比較」と特徴
換気システムは、給気と排気のどちらに機械(ファン)を使うかによって種類が分けられます。
- 第一種換気:給気・排気ともに機械で行います。システム全体での換気量を細かく制御できるため、計画通りの換気が確実に行いやすいのが特徴です。また、排気する際の熱を回収して給気に戻す「熱交換機能」を搭載できるのもこの方式が主で、省エネルギー性を重視する場合には特に有利な選択肢となります。
- 第三種換気:排気のみ機械で行い、給気は自然の力(給気口)で行います。構造がシンプルで導入コストは抑えやすい反面、換気量の制御は第一種に比べて難しくなります。また、冬場は外気がそのまま入ってくるため、室温が下がりやすいデメリットもあります。
熱交換機能の有無が冷暖房費に与える影響
第一種換気で採用される「全熱交換器(熱交換換気)」は、室内の温度だけでなく湿度も回収して戻すため、
冬は暖かく乾燥しすぎない空気を、夏は涼しくカラッとした空気を保つのに役立ちます。
この機能により、せっかく高性能な断熱材(UA値)で温めた空気をそのまま捨ててしまうのを防ぎ、冷暖房費の大幅な削減が期待できます。
ただし、熱交換システムの導入は初期費用が高くなるため、ランニングコストとのバランスを考えて選択しましょう。
高性能な断熱性能(UA値が低い)の住宅ほど、熱交換による省エネ効果はより大きくなります。
フィルター性能とメンテナンスの視点
換気システムの性能を最大限に活かすには、給気側に設置されるフィルターの選び方とメンテナンス計画が不可欠です。
花粉やPM2.5をブロックするためには、高性能な捕集率を持つフィルターを選択しましょう。
高性能フィルターは捕集率が高い分、目詰まりもしやすいため、定期的な掃除や交換が必須です。
フィルターの交換頻度やコストはメーカーや機種によって異なるため、計画段階でカタログやランニングコストの目安を必ず確認しておきましょう。
また、フィルターの交換が容易な場所にあるか、自分で簡単にできる仕組みになっているかも、継続的なメンテナンスを行うための重要なポイントです。
要点:第一種換気は熱交換により省エネ性が高いですが、初期コストがかかり、第三種換気は構造がシンプルで安価な反面、室温への影響が大きいことを理解しておきましょう。
⚠️ よくある失敗・誤解と回避策
換気計画は、その設計意図通りに機能してこそ価値があります。計画段階での誤解や、入居後の運用ミスによって換気性能が低下してしまうケースは少なくありません。
失敗1:換気口を塞いでしまう、または給気フィルターを交換しない
寒さや外の騒音を避けるために、給気口を閉じてしまったり、フィルター掃除を怠って目詰まりさせたりすると、換気システム全体の性能は著しく低下します。特に第三種換気の場合、給気口が塞がれると排気量が減り、シックハウス対策のための換気量(0.5回/h)を確保できなくなる可能性があります。
【回避策】高性能なシステムほど、給気口の位置や騒音対策、メンテナンスのしやすさに配慮して計画することが重要です。給気口はベッドやソファから離れた、手の届きやすい位置に設計しておきましょう。
失敗2:高性能フィルター選択による圧力損失の過小評価
アレルギー対策として高性能フィルター(微細な粒子を捕集できるもの)を導入する際、フィルターが抵抗となり、必要な換気量を確保できなくなる(圧力損失)ケースがあります。
【回避策】高性能フィルターを選んだ場合は、それに見合ったファンの風量設定や、ダクトの太さ、システムの能力を確保できているかを、設計者に確認してもらいましょう。また、フィルター交換時期をアラームで知らせる機能がある機種を選ぶのも安心です。
失敗3:家中の空気の流れ(ダクト計画)が考慮されていない
換気は、計画された空気の流れ(ルート)があって初めて家全体を巡ります。
排気口に近い部屋ばかり空気が入れ替わり、遠い部屋やクローゼットの奥など、特定の場所に新鮮な空気が届かない「換気ムラ」が発生することがあります。
【回避策】換気計画は、各部屋の扉のアンダーカット(隙間)や換気経路の設計図(ゾーニング図)とセットでチェックしましょう。寝室や子供部屋、リビングなど、主要な居室に必要な換気量が確保されているかを、設計時に確認することが大切です。
要点:換気システムの性能はメンテナンス頻度と、換気経路の設計によって決まるため、計画段階で換気ムラ対策とフィルター交換のしやすさを確認しておきましょう。
✅ 換気計画のセルフチェックリスト
▢ 導入予定のシステムが、アレルギー対策として花粉やPM2.5を捕集できる高性能フィルターに対応していますか?
▢ 高性能フィルターの交換頻度と部品代の目安を把握し、無理なく続けられる計画になっていますか?
▢ 就寝中の騒音が気にならないよう、寝室や静かな居室から給気口・排気口が十分に離れた位置に設置されていますか?
▢ 家中の扉のアンダーカットや、換気口の設置場所を含め、空気の循環経路にムラがないか設計者に確認しましたか?
▢ 冬場の乾燥対策として、熱交換システムによる湿度回収の仕組みを検討しましたか?
▢ 給気口の近くにエアコンの室外機や給湯器の排気など、汚染源がない配置になっていますか?
❓ よくある質問
- Q. 第一種換気と第三種換気で、空気のきれいさに違いはありますか?
- A. どちらの方式も法律で定められた換気量は確保できますが、空気の「きれいさ」という点では、高性能フィルターを標準装備しやすく、機械で強制的に空気を室内に取り込む第一種換気の方が、花粉やPM2.5対策を講じやすいと言えます。また、正圧制御が可能な機種は、隙間からの汚染物質の侵入を防ぐ効果も期待できます。
- Q. 換気システムは24時間つけっぱなしで大丈夫でしょうか?
- A. はい、基本的には24時間運転を継続することが必要です。換気システムは、住まいと家族の健康のために継続的に空気を入れ替え、建材からの化学物質や生活臭、水蒸気を排出する役割を担っています。電気代の心配があるかもしれませんが、多くはわずかな電力で稼働するように設計されていますので、停止せずに使い続けるようにしましょう。
- Q. 換気システムの電気代はどれくらいが目安でしょうか?
- A. 機種やメーカー、設定風量によって大きく異なりますが、一般的な第一種熱交換換気システムの場合、月に数百円から数千円程度が目安となることが多いです。ただし、熱交換のない第三種換気システムや、高性能なフィルターを使用し抵抗が増している場合は、消費電力が増える可能性があります。具体的な電気代は、採用予定のシステムのカタログや仕様書で確認することをおすすめします。
- Q. 部屋の換気口(給気口)から冷たい風が入ってくるのですが、閉めても良いでしょうか?
- A. 寒く感じる気持ちは理解できますが、給気口を閉めてしまうと家全体の換気バランスが崩れ、換気量が不足し、健康リスクが高まる可能性があります。冷たい風が入る場合は、窓やドアからの隙間風を防ぐための気密性能(C値)が不十分であるか、給気口の位置が不適切である可能性があります。まずは設計者に相談し、給気口の位置調整や、暖房器具との連携について対策を検討しましょう。
まとめ
換気計画は、高性能な断熱・気密性能を持つ現代の住宅において、家族の健康を守り、快適な暮らしを実現するための土台です。
特にアレルギー対策の観点からは、第一種換気の高性能フィルターと正圧制御の仕組みは、検討する価値のある選択肢となるでしょう。
重要なのは、初期コストやランニングコスト、そしてメンテナンスの頻度を総合的に判断し、ご自身のライフスタイルに合ったシステムを選ぶことです。
換気システムは設置したら終わりではなく、24時間使い続け、適切なメンテナンスを行ってこそ、その真価を発揮します。
本記事のチェックリストを活用し、きれいな空気で満たされた安心できる住まいづくりを進めていきましょう。
用語ミニ解説
- 第一種換気
- 給気と排気の両方を機械(ファン)の力で行う換気方式です。計画通りに換気量を制御しやすく、熱交換器を搭載することで省エネ性を高められるのが特徴です。
- 第三種換気
- 排気のみを機械で行い、給気は自然の力(給気口)を利用する換気方式です。構造がシンプルで安価ですが、冬場は外気がそのまま入るため室温が下がりやすい傾向があります。
- 正圧(せいあつ)
- 室内気圧が室外気圧よりわずかに高い状態を指します。正圧にすることで、窓や扉などの隙間からフィルターを通らない外気が侵入するのを防ぎ、きれいな空気を保ちやすくなります。
- 熱交換換気
- 排気する際、室内の空気の持つ熱(または冷気)を回収し、新しく取り込む外気に移して室内へ戻す仕組みです。これにより、換気による冷暖房負荷のロスを減らし、冷暖房費の削減に貢献します。
あ
LINEで送る